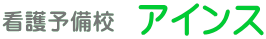はじめに
看護専門学校の社会人入試では、一次試験(筆記・小論文)の合格後、面接が最大の難関となります。
一次試験の合格者は多数いますが、最終合格者は大幅に絞り込まれるため、面接対策が極めて重要です。
面接では、受験生の「看護師になりたい理由」「志望校を選んだ理由」「入学後の抱負」「卒業後の進路」などが深く問われます。
また、想定外の質問への対応力や、自己分析の深さも評価の対象となります。
東京都立看護専門学校社会人入試対策模擬面接/30分/3000円
これまでのアインス生の受験報告に基づいて面接練習を行います。ZOOMでにみ行います。録画しますので、いつでもどこでも復習できます。
お申込みはコチラ ご相談の上、模擬面接日を決定させていただきます。
I. 看護師志望理由
面接で最も核となる質問は「あなたはどうして看護師になろうと思いましたか?」です。
この質問を通じて、面接官は以下の4つの点を重点的に確認します。
医療に対する理解度(介護との違い)
単なるイメージや理想ではなく、病気や怪我で苦しむ患者を回復へと導く具体的な場としての「医療」を理解しているかが問われます。
介護職経験者には「介護のままではダメなのか?どうして医療なのか?」と問われることが多く、介護が福祉の分野であり、医療行為ができないのに対し、看護師は医療行為を通じて患者の回復に貢献できる点を明確に説明する必要があります。
「介護と看護の違い」は、介護が福祉の分野で「医療行為ができない」のに対し、看護師は「病気や怪我で苦しむ患者様を回復へと向かわせる」医療行為ができる点です。
看護に対する理解度(医師との違い)
医師と看護師の違いは「患者様との距離の違い」であり、看護師は患者に最も近いところで仕事をする存在であると説明されます。
この距離の近さが、患者の身体的・精神的状態に対する「理解の深さ」につながり、治療へのフィードバックや回復支援に貢献します。
医師が診断や手術といった「ピンポイント」で患者に関わるのに対し、看護師は入院から退院までを「線」で支え、常に患者を第一に考える存在であることが強調されます。
看護師の具体的な仕事内容
診療補助、病棟での患者支援(食事介助、トイレ介助、入浴介助、バイタル測定、おむつ交換など)、急変時の対応といった具体的な業務内容を理解しているかが問われます。
看護助手経験者は高く評価されますが、未経験者も事前に看護師の仕事内容を学習したり、可能であれば看護助手の経験を積むことが推奨されます。
「看護を心ざした時からは看護師の卵です。」として、現場を知ることの重要性が語られています。
受験生の意思の強さ
看護師になるという決断が「主体的な決断」であるか、周囲の反対やコロナ禍のような困難な状況下でも「私は看護師をやりたい」という強い意思があるかが問われます。
経済的安定や資格取得の利点だけでなく、患者の死や苦情、過酷な労働環境といった困難を乗り越え、患者のために尽くせるかどうかの覚悟が見られます。
対策のポイント
自分の考えや感じていることを「文字化する」ことで、思考を明確にする。
「練習量が不安を打ち消してくれる唯一の方法」であり、何度も模擬面接を行うことが重要です。
早口にならず、言葉に「気持ちを込める」ことで、面接官に伝える熱意を示します。
II. 本校志望理由
次に重要な質問は「本校志望理由を教えて下さい」です。面接官は以下の点を重視します。
本校に対する理解度(他校との違い)
看護学校で学ぶことは概ね共通している(看護学、実技実習、病院実習)ものの、各学校には固有の「特色」があります。
例えば、都立広尾病院は外国人患者対応に注力し、荏原専門学校は地域医療、在宅医療、訪問看護に力を入れています。
「この学校でしか学べないこと、この学校でしか学べないもの」を具体的に示すことが求められます。
パンフレットを読み込み、説明会やオープンキャンパスに参加して、各校の特徴を把握しておく必要があります。
本校のアドミッションポリシー
社会人入試では、学校側が「取りたい生徒を採れる」ため、アドミッションポリシーに合致する人物像であるかが重視されます。
「人の痛みがわかる」「知的好奇心旺盛」「協調性やコミュニケーション能力に長けている」といった、学校が求める学生像に自分が適していることを示す必要があります。
加えて「一生懸命勉強してくれる人」であるかどうかも重要なポイントです。
説明会やオープンキャンパスへの参加
説明会やオープンキャンパスへの参加は、学校への関心度を示す重要な要素です。
参加した際には、その時の「印象や感想」(代表教員の丁寧な説明、模擬授業への感銘など)を具体的に語れるように準備しておく必要があります。
これは評価点を上げるために期待される「Yes」の回答であり、その経験から前向きな学びや意欲を得たことを伝えるべきです。
志望理由を語る上での構成要素
教員の優秀さ: 「優秀な先生のもとで看護学が学べる」という点は、最優先事項として挙げられます。
仲間たち: 「意識の高い仲間たちと共に切磋琢磨して勉強できる」環境も大きなポイントです。
環境・設備: 勉強できる環境、図書館、実習室など、恵まれた環境や設備も理由として挙げられますが、優先順位は教員や仲間の次です。
学費の安さ: 東京都立看護専門学校の「学費の安さ」は、経済的な心配なく勉強に集中できる利点として挙げられます。
自宅からの近さ: 「自宅から近い」ことも、通学時間の節約や勉強への集中に繋がり、また地域貢献の意思を示す上でも重要な理由となります。
交通手段と所要時間を具体的に説明できるように準備し、所要時間が長い場合は、合格したら近くに引っ越す意向を伝えることも有効です。
国家試験合格率・病院就職率: 高い合格率や就職率は、学校の質の高さを示す指標として挙げられます。
対策のポイント
学校ごとの特徴とアドミッションポリシーを徹底的に調べ、自分の経験や強みと結びつける。
具体的なエピソードを交えながら、学校への熱意を伝える。
質問への回答は、一方的に話すのではなく、面接官との「コミュニケーションのキャッチボール」を意識し、簡潔に答える準備をしておくこと。
III. 入学後の抱負/卒業後の進路
「入学後の抱負や卒業後の進路を聞かせて下さい」という質問は、受験生の将来への明確なビジョンと、看護師としての適性、および学校への貢献意欲を確認するために行われます。
看護学校で何を学ぶのか明確か
入学後に何を学びたいか、その目的意識が明確かを確認します。
解剖生理学、病理学、薬理学、生化学などの「看護学の学習」、ベッドメイキングや採血などの「看護技術の習得」、そして「病院実習を通じた臨床経験」といった具体的な学びの対象を述べます。
専門学校の目的は「即戦力」の養成であり、卒業後すぐに「地域の中核病院(二次医療機関)」で働く人材を育てることが期待されています。
「すぐに現場に出て患者さんの役立ちたい」という意欲を伝えることが重要です。
将来の目標が明確か
将来、どのような分野で活躍したいか、具体的な目標を持っているかを尋ねられます。
高齢者医療・在宅看護・訪問看護:少子高齢化社会において需要が高まる分野。
がん緩和ケア:日本人の死因1位であるがん治療・ケアへの関心。
小児・周産期医療:少子化の中でもリスクの高い新生児ケアへの関心。
精神看護:ストレス社会における精神疾患患者の増加と地域包括ケアシステムでの対応。
救急救命:緊急時の対応と命を救う使命感。
感染症対策:コロナ禍を背景にした感染症予防・対策への関心。
人工透析:生活習慣病の増加による透析患者の増加への対応。
公衆衛生:病気や怪我の予防、健康維持への貢献。
ただし、学校側は「幅広い分野で働ける人」を求めているため、特定の分野への関心だけでなく「様々な領域を一生懸命に勉強します」という姿勢を示すことが重要です。
都立病院への就職意向
都立看護専門学校の面接では「あなたは東京で働けるか?」と問われることがあり、都立病院や公立病院、または東京の医療機関で働きたいという意向を示すことが期待されます。
また、「自分を必要としてくれるところで用いられたい」という気持ちを伝えることで、面接官に強い印象を残すことができます。
対策のポイント
入学後の学習計画や将来の目標を具体的に語れるように準備する。
自分の興味・関心と社会のニーズ、学校の教育方針を結びつけて話す。
「明るい声で、目を輝かせながら」話すことで、看護師への強い希望と意欲を表現する。
専門学校が「即戦力」を重視し、二次医療機関で働く人材を求めていることを理解し、それに沿った抱負を述べる。
IV. 想定外の質問への対応
面接では、これまでの質問以外にも様々な角度から質問が飛んできます。
これは受験生の「コミュニケーション能力」「情報量(知識量)の多さ」「動揺の程度」などを測るためです。
よくある(想定内)の質問
自己紹介と受験番号
昨夜はよく眠れましたか?:緊張を和らげるための雑談。正直に「緊張してあまり眠れませんでした」と答えても良い。
一次試験(小論文)の出来栄え:何を書いたか、どう取り組んだか、内容を思い出せるように準備する。
自宅から本校までの交通手段と所要時間:具体的に説明できるように準備。所要時間が長い場合は、合格後の引っ越しを検討する旨を伝える。
緊張していますか?:これも雑談の一部。
これまでの仕事内容と、特に力を入れたこと:自己推薦書の内容と合致させ、簡潔に説明。
困ったことや困難なこと、それをどう解決し何を学んだか:具体的なエピソードを交え、問題解決能力と学びをアピール。これは看護師として直面する困難への対応力を測る重要な質問です。
転職が多い理由、空白期間に何をしていたか:正直に説明できれば問題ない。面接官は「過去のあなたよりもこれからのあなたの伸びしろ」を重視しています。転職や看護学校中退の経験があっても合格実績があるため、マイナスに捉える必要はありません。
ご家族の協力、友人・知人の反応:家族の協力体制が整っていること、周囲が応援してくれていることを伝えることが望ましい。
体力、ストレスへの強さ、ストレス解消法:看護師の仕事の厳しさを理解した上で、体力や精神的な強さを示す。
経済的な見通し:バイトで学費を稼ぐという回答はNG。奨学金制度などを活用する意向を伝える。
年下の同級生との関係性:前向きに「うまくやっていける」と答える。
長所と短所:長所は主体的、積極的、好奇心旺盛、コミュニケーション能力など。短所は長所の裏返し(例:責任感が強い→仕事を抱え込みがち)で、改善策も添える。
趣味・特技:ありきたりな内容で問題ない。「特技なし」でも全く問題なし。
子育て中の場合、子供が病気になった時の対応:家族の協力やサポート体制があることを具体的に説明。
想定外の質問
「なぜ今なのか?」:この質問は、単にタイミングを問うだけでなく、「看護師になりたいという決断の強さ、覚悟」を問うものです。
コロナ禍をきっかけに決意を固めた、経済的・家庭的な準備が整ったなど、具体的な理由を準備しておきましょう。
大学卒業者への「卒業論文のテーマ」「研究テーマ」「先行分野」:内容を思い出せるように準備し、それが看護師としての学びにどう繋がるかを説明できると良いでしょう。
「同級生が学業不振で悩んでいたらどう対応するか?」:共感し、耳を傾け、共に乗り越えようとする「共調性と思いやり」を示すことが求められます。
「自分は看護師に向いていると思うか?」:迷わず「はい」と答え、自分の長所や適性を具体的にアピールします。
自己PR:面接の最後に、自分の長所を軸に、看護師としての適性と熱意を力強くアピールする。
「是非私を合格させてほしい!」といった強い気持ちを伝えることも有効な場合があります。
具体的な専門分野への深掘り質問の例
災害医療:災害のフェーズ(超急性期、避難所前期・後期、仮設住宅期)ごとの患者の状態変化や、必要とされる医療従事者の役割(外科、内科、精神科、訪問看護)を理解しているかを問われます。
がん緩和ケア:がん患者が増えている理由(高齢化など)や、臓器移植の現状と課題(ドナー不足など)について知識があるかを問われます。
精神看護:精神疾患患者が増えている理由(ストレス社会、受診ハードルの低下、社会の理解の進展など)を問われます。
対策のポイント
日頃から医療に関するニュースや社会問題に関心を持ち、自分なりの考えをまとめる。
想定される質問だけでなく、そこから「深掘り」される可能性も考慮し、多角的に準備する。
面接官が「よく勉強しているな」と感じるような知識量を示す。
何よりも「練習量」が重要です。模擬面接を繰り返し行い、緊張の中でもスムーズに、熱意を持って答えられるように準備しましょう。
V. まとめ
看護専門学校の社会人入試面接は、受験生の看護師への強い志、人間性、学習意欲、そして問題解決能力などを総合的に評価する場です。本ブリーフィングドキュメントで示した各ポイントを深く理解し、具体的なエピソードや自身の言葉で語れるように準備することが、合格への鍵となります。